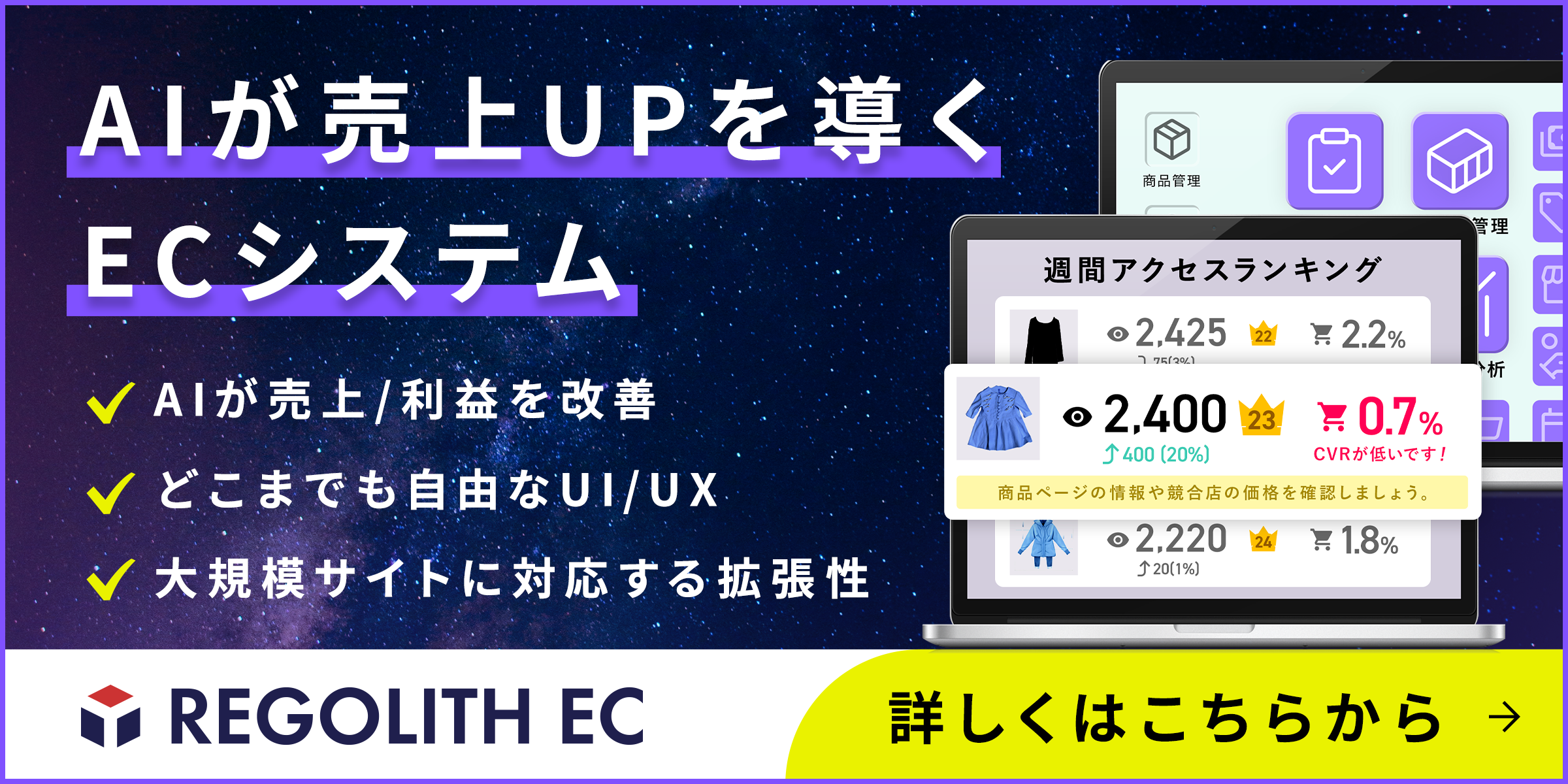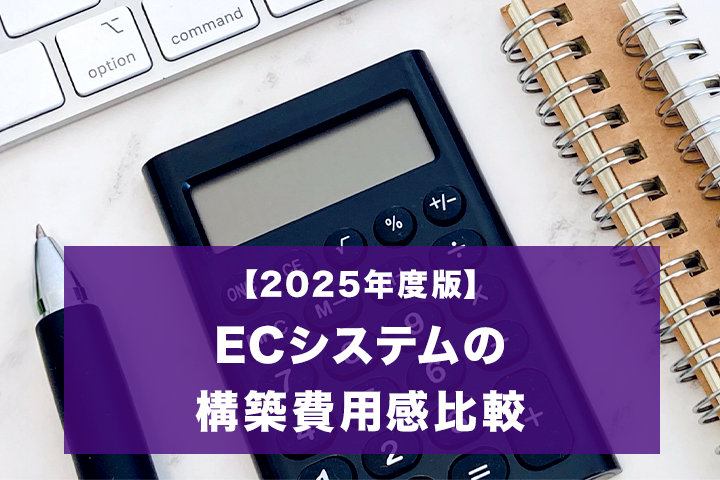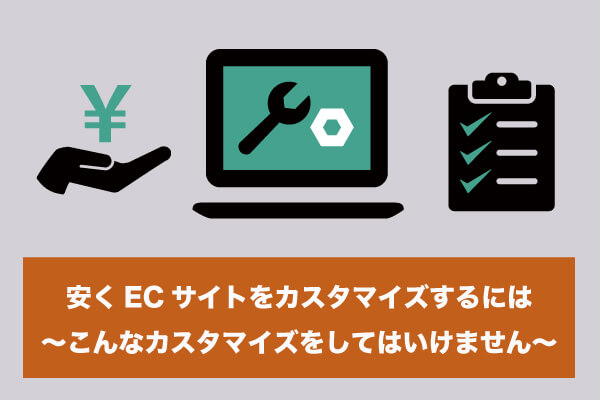目次
BtoBコマース/デジタルセールの普及の背景
初めに、EDI、BtoBコマース、デジタルセールス、など、企業間取引のシステムでよく聞かれる言葉に関して、その普及の背景も交えてご説明したいと思います。
EDIからBtoBコマースへ
企業間取引におけるデジタル化の歴史は長く、ECという言葉が一般化する以前から、EDI(Electronic Data Interchange)という仕組みが存在していました。EDIは、企業間で注文書や納品書などの商取引データを電子的にやり取りするための仕組みです。専用回線や特定の通信プロトコルを使用し、セキュアにデータ連携ができる反面、導入・維持に高コストがかかるため、取引量が多く、システム投資に積極的な企業に限られていました。
しかし、時代は変わり、インターネット環境とブラウザベースのアプリケーションの進化により、専用ソフトや回線を必要としない、よりオープンで低コストなBtoB向けECサイトが登場。取引規模に関わらず導入しやすいこの形態は、EDIの課題を補完し、多くの企業で採用が進んでいます。
BtoBコマースからデジタルセールスへ
「デジタルセールス」という言葉は、顧客の行動履歴や取引データを活用して、営業活動をより効率的かつ精緻に行う手法を指します。 一般に知られるようになった「SFA(営業支援システム)」や「CRM(顧客関係管理システム)」も、デジタルセールスに用いられるシステムの一部です。
コマースサイトは、デジタルセールスに欠かせない行動履歴や取引データの収集に最適なチャネルであるため、受発注業務のみならずデジタルセールス機能も備えたシステムが増えてきています。
BtoBサイトを構築するメリット
BtoBサイトを構築することによるメリットは大きく以下4つになります。
① 受発注業務の効率化
最も多い導入目的です。FAX・電話・メールなどのアナログな受注手段をWeb化し、業務の属人性を排除します。これにより、社内の工数削減だけでなく、取引先の利便性向上にもつながります。特に物流や製造業など、多頻度かつ定型的な取引が多い業種で効果を発揮します。
② 新規顧客・見込み顧客の獲得
Web上で製品情報やサービス情報を公開することで、今まで接点がなかった企業との新たな取引機会を創出できます。価格非表示やログイン後表示、問い合わせフォーム経由での資料請求など、BtoB特有の柔軟な公開設定が可能です。
③ 顧客対応・サービス品質の向上
「在庫はあるか?」「見積もりが欲しい」などの問い合わせ対応は、販売側だけでなく購入側にとっても手間です。ECサイトを活用することで、こうした作業をセルフサービス化でき、双方向にメリットが生まれます。また、24時間注文受付が可能となることで、夜間や休日にも対応でき、サービスレベルの向上にも寄与します。
④ 営業活動の自動化・効率化
取引先が多く、営業担当のリソースが限られている場合、営業活動の一部自動化が大きな効果をもたらします。リピート購入のタイミングでの自動通知、キャンペーンのターゲティング配信などにより、フォロー漏れの防止やロイヤルカスタマーの育成が可能になります。
システム選びのポイント
BtoBコマースのニーズ拡大に伴い、ECシステムも多様化しています。ただし、導入の成否は“目的に合ったシステム選定”にかかっていると言っても過言ではありません。
各社が提供するシステムに関して、差が大きいポイントをいくつかご紹介します。
自社でも確認が必要なポイントがあれば、選定の際に確認してみてください。
① カスタマイズ性の有無
パッケージ製品で対応できるケースもありますが、製品や業務プロセスに固有のルールがある場合、システム側に柔軟性があるかどうかが鍵となります。特に、製造業やOEM商材など、オーダーごとに仕様が異なる取引では、標準機能だけでは対応が難しいこともあります。
② BtoB特有の機能が備わっているか
単にBtoCのECサイトを非公開設定しただけの仕組みでは、以下のようなBtoB固有の運用には対応しきれません。br
- 商品管理:ロット/入数管理、最小販売数量管理
- 価格管理:掛け率管理
- 受注管理:見積書発行、納期回答
- 出荷管理:出荷分割、出荷倉庫管理
- 取引先管理:組織管理、請求管理、与信管理 など
これらの機能があらかじめ備わっているか、または追加開発が可能かどうかが重要です。
③ マーケティングオートメーション機能
営業リソースを補完する手段として、メール配信・商品レコメンド・購入促進など、マーケティング機能の有無も大きな判断材料となります。特に小口顧客が多い業態では、人的リソースに頼らず接点を保つ手段として必須です。
④ デジタルセールス支援の仕組み
ユーザーの行動ログを可視化し、それを営業アクションにつなげる仕組みがあるかどうかも、将来的な活用においては大きな差となります。営業担当へのアラート通知、ホットリードの可視化などは、成約率の向上にも寄与します。
⑤ BtoCサイトとの統合運用
BtoBとBtoCの両チャネルを運用している場合、在庫・商品・顧客データを共通化できるかどうかも重要です。2つのシステムを別々に管理するのではなく、一元的に管理できれば、業務効率だけでなくデータ活用の精度も高まります。
まとめ
BtoBコマースは、今や単なる「業務の効率化ツール」ではなく、営業戦略の一環として重要な役割を担う存在になりつつあります。受発注から営業支援、マーケティングまでをシームレスに連携させることが、これからのBtoBに求められる姿です。
当社「REGOLITH EC」では、こうした進化に対応する柔軟で拡張性の高いBtoBコマースシステムを提供しています。構築やリニューアルをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。